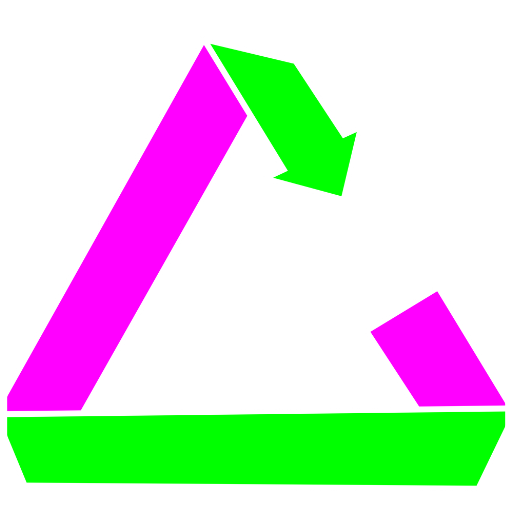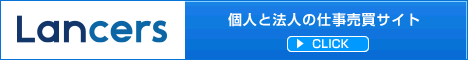伝えたいことがあるのに文章化できない。
インタビューをして記事にして欲しいけど、会社にライターがいない。
「インタビュー」とはインタビュアー(聞き手)が新聞や雑誌、Webコンテンツの文章作成のために、インタビュイー(話し手)から情報収集をすることです。
「会社のあの人は文章が書けるから会社の人に頼もう」と思ってもライターは、インタビューされる人が、インタビューを通じて伝えたいことをよく理解した上で、取材・執筆をしなくてはいけません。
また、その記事の目的に対して、予めインタビューする内容、重要なポイントを聞き出すテクニックも必要です。
今回はインタビューを業務委託する上で知っておきたいポイントをまとめました。自分でインタビューをやってみよう!と思う方への注意点もまとめています。
これを読むことでインタビュー記事に対しての不安や疑問がなくなりますので、ぜひ最後までお読みください。
Contents
インタビュー記事とは?
インタビュー記事とは、既存相手にさまざまな情報を聞き出しコンテンツ化(文章)にすることを指します。
インタビューといっても、さまざまな使い方ができるので近年ではインタビュー記事を取り入れる企業も増えています。
言い換えればインタビューとは相手への調査です。「調査」するということは、対象者へのインタビューを通じて、詳細な行動実態やその背景にある意識・感情・価値観などを深く掘り下げていく事です。
インタビュー記事のメリット・デメリット
インタビュー記事のメリット
人が何かを判断・選択したり、行動したりする背景には、さまざまな要因が複雑に影響しています。その本人であっても、決断や行動の理由を理解していないことも少なくありません。
インタビューでは、対象者の言葉から実態や意識・感情などを深掘りしながら質問を繰り返し、事実ベースで捉えていきます。
そして、その背景にある要因や因果関係を掘り下げていくことがインタビューの目的です。
そのためインタビューを効果的に使うと調査結果は、商品開発やマーケティングの様々な場面に活かすことができます。
- 既存顧客にインタビューし、導入事例や課題としてまとめることで、見込み顧客に製品や商品の魅力を伝えられる
- 営業シーンで顧客に見せることで、説明資料や検討材料としても利用できる
- 新しい商品開発の過程や想いを文章化することで製品をストーリー化して見込み客の関心を引くことが出来る。
- 会社の採用情報の場合、現場の雰囲気や従業員の生の声をコンテンツ化でき会社の魅力が伝わりやすくなる
また、状況や目的によってはパンフレットや見出し一面にインタビュイー(インタビューされる人)の、自然な笑顔やインタビューを受けている時の雰囲気、またインタビュー内容とは少し違う、インタビュイーの趣味などを交えた写真を使う場合もあります。
リアルな画像を加えることで、記事を読んだ人にインパクトのある感情や関心を与えることができるのもインタビュー記事のメリットです。
インタビュー記事のデメリット
インタビュー記事のデメリットは、インタビュアー(インタビューをする人)が、いかにインタビュイーについて、しっかり事前下調べができているか?が重要なポイントとなります。
1人に対して60~90分程度の時間を割くため、時間的・コスト的な効率が悪いのが最大のデメリットです。
そのため、下調べなしで魅力的なインタビュー記事は完成しないため、下調べの時間確保が必須です。忙しいインタビュアーにとってスケジュール管理は非常に重要なPOINTになります。
なるべく相手のスケジュールに合わせて、それまでに下調べ(下準備)を済ませ、企画書を作成しておくことと、スムーズにインタビューを行えます。
また、インタビューは現地取材、オンライン取材を含めてお互いの時間を調節しなくてはいけません。
その他にも、対象者の言葉や反応を見ながら臨機応変に質問する必要があるため、インタビュアーのスキルによって調査結果が左右されやすいでしょう。
インタビューの目的とは?

インタビューをしたいと思うときの状況は企業や個人の目的によってさまざまです、インタビューを行う際の調査目的や内容をしっかり決めたうえでインタビューに挑みましょう。
この章ではインタビューの目的、活用事例について解説します。
自分自身をインタビューして会社のPRに使いたい
会社の代表など、自分自身をインタビューして会社の特徴や魅力、理念を文章化して欲しい経営者は多くいます。
伝えたい想いはたくさんあるのに「どうも文章は苦手だな・・」と思う方でも、経験あるインタビュアーにインタビューされることで熱い想いを文章化することが可能です。
また、会社の経営者ではなく従業員が社長のインタビューをご依頼されることも多くあります。
会社のPRの一環としてインタビューを取り入れることで、ただ文章化しただけでは効果がなかった見込み客の反応が、インタビュー記事によって大きく変わることも多くあります。
インタビューして欲しい人が決まっていてコンテンツを作りたい
会社従業員や取引先の社長、セミナーやイベントの内容など、対象者が決まっている場合でも、何を取材したら良いのか分からない・・・。そんな「ふんわり取材したい」と思っている場合もあるでしょう。
会社のPRなのか、理念なのか、製品作りやサービスに至るまでの想いや経緯なのか、「ふんわり取材したい」場合でも問題ありません。
誰を取材したいのか?が明確になっていれば、当社「月極めライター」が詳しくヒアリングを行います。
また、対象者が決まっていない場合でも、ただ取材記事が欲しい。それだけで十分満足なコンテンツづくりができるのか?ご不安な方も一度無料相談からお問い合わせください。

お客様の声をコンテンツにまとめたい
会社の製品やサービスを使ったお客様の声を直接聞き、臨場感あふれるコンテンツを作りたい場合お客様から直接聞けるインタビュー記事の効果は絶大です。
普段は、さらっとしかネット上の文章を読まないユーザーでも、気になっている商品のレビューやお客様の声はじっくり読む。という方も多くいらっしゃいます。
それだけ愛用者の声やレビューや感想は、商品を決める際の重要な指標になっていることが分かりますね。
当社では「お客様の声」を取材インタビューする際は、商品やサービスを決める前の気持ちや背景から、サービスにたどり着いた経緯を聞き出します。
詳細について核心に迫ることで、実際に使ってみた感想はもちろん、その商品やサービスを使うことによって手に入れた未来(利益、得)なども深掘りが可能です。
特に、サービスや商品の魅力だけを伝えるお客様に対しても、もっと深く潜在的に眠っていたニーズを聞き出すインタビューに、当社は注力しております。
お客様の声をインタビュー形式に変えたことで、売上の20%増を獲得したクライアント様など多くいらっしゃいますので、お客様の声インタビューは当社「月極めライター」の得意ジャンルです。
新商品の企画・開発や既存商品の改善や顧客の実態、意思決定プロセスを詳細に把握したい
こちらも、お客様の声とよく似ているケースですが、顧客の実態を知ることは今後のサービス展開にもっとも役立ちます。
「このサービスには満足しているけれど、もっと○○だったら・・」、この〇〇を深掘りします。
そもそも最初にあったニーズ(顕在ニーズ)から、〇〇に行き着いた、潜在ニーズまで深掘りすることで今後の新製品の企画や改善に役立つインタビュー記事が出来上がります。
調査でわかった課題・ニーズについて深く掘り下げたい
インタビューをする際に「課題」を企画することで、その課題に対してのニーズはどれだけあるのか、ターゲットにインタビューすることで、より深くニーズが分かります。
自社ではこのニーズがあるはずだ!と持っていても、ターゲットにインタビューしてみると、全く違う分野にニーズがあったり、意外な盲点を発掘したりできます。
このように今後の課題変更やニーズの需要についてインタビューで明らかにすることが可能です。
課題を作り仮説を立てたい、または仮説を検証したい
一人のユーザーに対して自社で課題を作り、想定できる限りの仮説をたて、どのような反応が返ってくるのか検証したい場合もインタビューが役に立ちます。
仮説ですので失敗すれば、新たなニーズを探れば良いでしょう。プロダクトの失敗を防ぐために大切なのは消費者が求めているものが何か、です。
仮説を立て、それが正しいかどうかを仮説検証に有効な手段なのが「ユーザーインタビュー」です。
カスタマージャーニーやペルソナを作成したい
カスタマージャーニーとは、顧客の購買行動における一連のプロセスのことです。一般に購買行動は「商品・サービスの認知→興味・関心→比較検討→購入→利用→再購入」の流れをたどります。
カスタマージャーにの設置におけるペルソナ設定で役立つのがグループインタビューです。
インタビューには対象者を4~8名程度集めて座談会形式で実施をすることでより精密なペルソナ設定ができます。
まずは、カスタマージャーニーマップのフレームを埋めるための顧客情報を集めインタビュー形式で仮説を立てながら行うのが良いのでしょう。
アイデアやコンセプトについての反応を知りたい
なんとなく、ふわっとしたアイデアが見つかった、コンセプトの方向性が決まったけれど社内で大々的に商品開発を進めるには、まだ情報が少なすぎる場合には「コンセプト調査」が必須となります。
まずは製品やサービスの特質を絵や文章で説明したものを用意します。
インタビュー調査時は、製品化の前段階で、「ターゲット顧客が購入を喚起する商品コンセプトになっているか」を明らかにします。
コンセプト調査にインタビューを用いることによって、まず調査方法ごとにある「特徴」を活用できる、商品化する前にユーザーニーズを明確に把握できるなどのメリットがあり、余計なコストを削減できます。
また、インタビューによって消費者の意見を把握した上で商品開発を進められるため、事業の効率化が測れるというメリットもあります。
広告表現についての印象や評価を知りたい
インタビュー方法(福岡県内・全国取材インタビュー可能)

インタビュー方法には現地へと訪問して直接対面取材する方法と、オンライン(ZOOMやGoogle)で取材を行う方法があります。
当社では福岡県内であれば、直接現地へ訪問取材を行っています。
特に当社は全国的に取材インタビューのご依頼が多いため、その場合は電話通話やgoogleやZOOMなどのオンライン通話を使って取材インタビューを行っています。
お気軽にお問い合わせ下さい。
現地訪問
現地訪問の際はあらかじめ、インタビューを行う相手へのアポ取りから始めます。
その他、場所の確保や日時の調節などの細かい設定を、お互いのズレがないように整えなくてはいけません。
アポ取り、場所の設定などは、予定している日時の1ヶ月〜1ヶ月半前から余裕を持って取るようにします。
また、現地取材当日までにカメラマンの手配、または自分で撮影するならカメラなどの準備も必要です。
特に録音機材であるボイスレコーダーや携帯電話の録音機能など、当日になって「使えない!」ことがないように、慎重に準備をしておきましょう。
近年では録音した内容を、そのまま文字起こしをしてくれる便利なツールも多くあります。インタビューに文字起こしはつきものです。
事前に文字起こしツールを使っておくことで、文字起こしをする時短につながりますので、是非、取り入れておきたいツールですね。
オンライン通話
オンライン通話で重要なのは録音です。上記の現地取材と似ていますが、オンライン通話ではカメラ(画面上)の表情や雰囲気も録画することが可能です。
しかし、オンライン通話の録画機能だけでは不安ですよね。同時にスマホのボイスレコーダーも使って音声だけでも録音しておくことをおすすめします。
ちなみに、当社ではオンライン、現地取材ともに4台の録音機材を使って取材を行っています。これは私自身が「ウッカリさん」なので、不安を払拭するために使える機材はフル稼働させているのです。
自分でインタビューしてみる際の注意点を解説
続いて、自社でインタビュアーに挑戦してみようという方に向けての注意点を解説します。
インタビュアーはインタビュイーの予定調整も考えて、インタビュー希望日から1ヶ月は空けて依頼することをおすすめします。
特に著名人や会社の代表など、多忙な方は3ヶ月ほど予定が埋まっている場合もあります。
直近の日程で設定し、先方を急かしてしまうのは失礼にあたります。余裕をもって時前準備に取り掛かりましょう。
インタビュー前の準備
インタビューは時前準備が7割といわれています。まずはインタビュイー(相手)が所属する企業や団体があれば、そのホームページを調べることから始めましょう。
広報欄などがあれば、そこから問い合わせます。個人のTwitterやインスタグラムなどのSNSを使う手も有効ですが、会社や企業への取材の場合はあまりお勧めできません。
なぜならSNSは企業の発信のプラットフォームであり、お問い合わせの窓口ではないからです。
もし、会社フォームページに取材・講演依頼用の問い合わせフォームがなければ、一般的なお客様お問い合わせフォームを利用するのもよいでしょう。
ただ、この方法はインタビュイーへの間接的な依頼であるため、返信が来るまでに時間がかかることもあります。
返信がない場合や時間を要する場合などに限り、SNS(Twitter、インスタ、フィエイスブック)を活用したり、人づてに紹介してもらったりするのが理想です。
取材前準備
インタビューと一言にいっても、特に取材前の準備は重要です。
取材前であればアポ取りから、下調べ、ターゲットを絞った質問内容の収集など、やらなければいけないことは多くあります。
- インタビュイーのことを徹底的に調べる。
- 絶対に聞いておきたいこと|時間があれば聞きたい事を分けて整理しておく
- 質問票(企画書)を事前に共有する
- 当日の流れを把握し可能であればシュミレーションをしておく。
それでは上記の4点について詳しくみていきましょう。
インタビュイーのことを徹底的に調べる。
インタビュー取材において、インタビュイーのことを徹底的に調べ上げるのことは基本です。
取材中にはいつどんな状況で、思わぬ話の糸口が見つかるか分かりません。課題に対しての核心に迫ることのできる話に繋がったり、意外な話も聞けるかもしれません。
そのためには相手のことを徹底的に調べ、専門分野についても、ある程度の知見があるくらいになるまで分からない言葉や専門用語があれば事前に調べておきましょう。
例えば相手が著名人なら出版している著者や、過去に受けたインタビュー動画や記事、一般人であれば個人のSNSや会社ホームページなどは、完全に把握しておくべきです。
私は、一般人の方に取材をする際はまずSNSから調査します。SNSには個人的なつぶやきも多くみられ、個人の意外な趣味や興味があることなどを知れるからです。
「この先、どう話を繋げたら良いのか分からない…」という沈黙に対して、「必殺!奥の手の話題」を頭の片隅に置いておくだけでもOKです。
沈黙を恐れることなく、緊張をほぐすきっかけになるでしょう。
絶対に聞いておきたいこと|時間があれば聞きたい事を分けて整理しておく
一般的な取材時間は1時間〜1時間半ほどが多いです。
突然時間短縮になり取材が終了してしまうというハプニングも想定しておかなければいけません。
絶対に聞いておきたいこと(メインの課題・重要ポイントレベル)、時間があれば聞いておきたい事(世間話程度のレベル)を、自分自身が分かりやすいように整理しておきましょう。
取材時間は永遠に続くわけではありません。絶対聞く!時間があれば聞く。をどの順番で、どう言った流れで聞くのか分けておくことが大切です。
その際のポイントとして、話の道筋を見失わない様に起承転結を意識しながら聞いておきたいことをまとめると進行の流れに迷わずに済むでしょう。
特にインタビュー用の雑談ネタを仕込んでおくと、スムーズな雰囲気でインタビューを進められるのでインタビュアーにとっても「雑談ネタ仕込み」は、おすすめです。
質問票(企画書)を事前に共有する
インタビュー関係者はもちろん、インタビューする相手にも質問リストを作成しは事前に共有しましょう。
そうすることで、インタビュイーにとって「何を質問されるのか」といった無駄な緊張がなくなります。その上で、質問の回答を準備しておくこともできます。
また、インタビュー関係者に「〜について〇〇さんがどのように考えているのかを、お聞きしたいです」などの要望があっても、質問内容を相手に事前共有しておくことで当日の取材が、よりスムーズになるでしょう。
当日の流れを把握し可能であればシュミレーションをしておく。
当日のインタビューの流れに対しての時間配分を考えておくことは重要です。
取材の機材を揃えたりする準備中もインタビュー取材です。相手がいるならば「もう取材中である」という認識を持ち、会話を始めましょう。
その際、先ほど挙げた事前に調べた雑談ネタを使うのも有効だと思います。その内容を含め取材時間を逆算しながら、当日の流れを事前にシュミレーションをしておきましょう。
どの質問に対して、何分時間を使うのか?事前にシュミレーションをしておくことで当日に混乱しなくて済みます。
シュミレーションは重要ですが、全くその通りに進めなくてはいけないといった事はありません。
どのようなシュチュエーションでも柔軟に対応できるように、余裕があれば何通りかのシュミレーションをしておくと、より心強くなりますので、ぜひ応用してみてくださいね。
取材現場での注意点
インタビューに慣れていないうちは、質問することに必死でついついメモばかりを見がちになります。
「取材相手の立場になって質問する姿勢」を意識して、なるべくメモを見ないようにしましょう。
シュミレーションをした通りに質問ができず、質問内容が飛んでしまっても問題ない!くらいの気持ちで相手の目をしっかり見つめながら、話に耳を傾けましょう。
そうすることで「この話、もう少し深掘りしたい」「核心に迫る道筋が見えた!」など、メモに集中すること以上に大切な瞬間が訪れるかもしれません。
その瞬間を見過ごさないためにも、しっかり相手の話を聞く姿勢には注意が必要です。
「この話のここを深く聞きたい」などの場合は箇条書きでメモを取るのは良いと思いますが、メモすることに必死になっていては取材相手からすると、全く面白くありませんよね。
今はボイスレコーダもありますし、メモすることは余程のことではない限り控えるようにして相手の話を聞く姿勢を崩さないようにしましょう。
インタビューとは「相手との対話|会話」です。大切なのは相手の目を見て話をする、聞くことを忘れないようにしましょう!
インタビュー記事執筆前|文字起こし

インタビュー記事の執筆前には、インタビューで録音した内容を文字起こしする必要があります。
近年はインタビューを録音しながら文字起こしを同時に行なってくれる便利なツールも存在しています。
一般的に文字起こしの作業にかかる時間は、音源の録音時間の約4倍と言われています。
聞いて、止めて、文字を打って、聞いて・・・タイピングの遅い方なら、それ以上かかるでしょう。
特に初心者の場合は1時間の音声データを文字起こしする際に6〜8時間ほどかかります。
慣れているライターでも4〜5時間かかるため、文字起こしを依頼する際は時間を多く見積もっておく必要があります。
文字起こしツールを使って、雑音や誤変換の部分だけを文字起こしするなどの工夫をすることで時短につながりおすすめです。
今では、スキルを売り買いするサービス「ココナラ」「クラウドワークス」などでも、安価、短時間で文字起こしを代行してくれるサービスもあります。時間のない方は文字起こしサービスも、一度検討してみるとよいでしょう。
当社の場合は、録音と同時に文字起こしツールを使用し、誤変換部分だけを手打ちで修正しています。
文字起こしが終わったら、いよいよ重要部分と、そうではない部分の取捨選択を行い、文章執筆に入りましょう!
インタビュー記事|執筆のコツ

- 会話型
- 一人称型
- 三人称型
1)一人称型
2)会話型
3)三人称型
つまり「取材をした感想をライターが書いた」という体の文章になります。
最後に

福岡「月極めライター」では、ライター歴の長いインタビュアーが、事前ヒアリングを入念に行い文章(コンテンツ)の目的やアピールしたいポイントをあらかじめ聞いた上で、インタビュー当日までにしっかり企画書を作ります。
インタビュー当日は、ZOOMもしくは現地にて取材を行います。取材といっても堅苦しいものではなく世間話から始まることも多くありますので、お互いが緊張しない、緊張させないインタビューが基本です。
ぜひ、一度お問い合わせくださいませ。
また「一度、自分でインタビューに挑戦しよう!」と思っている方は、この記事を参考に肩の力を抜いて頑張ってみてくださいね!
何かにつまづいた際にはお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。